

Mike Rutherford
ご存知Genesisのメンバー。Genesisの中でこの人の作る音楽が一番好き。あ、Anthony Phillipsは別格、ということで。
 | Smallcreep's Day ('80) | Mike Rutherford(g、b)の1stソロ。盟友Ant Phillips(key)を迎え、Simon Phillips(ds)、Morris Peart(perc)にMoonに在籍していたNoel McCalla(vo)という布陣で製作する。まずは、7つのセクションからなる"Smallcreep's Day"組曲から始まる(所謂A面を全部使ったものかな?)。この組曲は、Peter Currell Brownの小説"Smallcreep's Day"からインスパイアされたもの。ブックレットに小説の簡単なストーリーが書いてある。本は未読なので、正確には判らないが、産業革命時代を背景にした本のような感じがする。本作は、Ant Phillipsの厳かなキーボードの音色にしっかりしたNoel McCallaの声が乗り、Smallcreepの一日が始まる。アコースティックギターが印象的な"Working in Line"へと続き"After Hours"(インスト)から"Cas and Rats(in This Neighbourhood)"へ。"Smallcreep Alone"と"Out into the Daylight"というインスト曲を挟んで、エンディング"At the End of the Day"で組曲は締めくくられる。LPで言うところのB面にも5曲収められている。インストを中心に兎に角、あちこちにGenesisよりもGenesisらしい音が沢山散りばめられている。バンド形態に拘り、他のメンバーのソロ活動を見やりながらも、Mike Rutherfordが練りに練った音。ジャケットから何から何まで全てが素晴らしい傑作。プロデュースもDavid Hentschel。 |
 | Acting Very Strange ('82) | Mike Rutherfordの2ndソロ。全8曲。バンド形態の前作と打って変わって、豊富な数のゲスト陣を揃えている。まず、ギターにGenesisのツアーメンバーにも抜擢されているDaryl Stuermer、John Alexander(後にPost Mortem)、キーボードにPeter Robinson(元Quartermass)にPaul Fishman、ドラムにStewart Copeland(Police)とPete Phipps(元The Glitter Band)。サックスにGary Barnacle、トランペットにLuke Tunney。ストリング・アレンジメントにMartyn Ford。バックボーカルに前作に起用されたNoel McCallaを始め、Steve Gould(元Rare Bird)、Dale Newman(Seconds Outに参加)。このアルバムの基本は何はともあれ、Mike Rutherford本人が自分でヴォーカルを取ってみたかった、という事なんだろう。キャッチーでポップな曲が続くが、ゲスト陣の濃さ等は特に伝わって来ない。時代柄、ということなんだろうか? |
Mike + the Mechanics
 | Mike + the Mechanics ('85) | 当初、日本ではMike Rutherfordの3枚目のソロ扱いであったMike + the Mechanics。ソロからの経験を活かして、このプロジェクトでは、バンドコンセプトをがっちりと作ることから始めたようだ。まずは、B.A.RobertsonとプロデューサーでもあるChristopher Neilといった作曲パートナーを選出。強力なヴォーカリストを持つバンドサウンドをメインに、Christopher Neilの洗練されたプロデュースワークで仕上げる、というコンセプトがまずはありきなのだ。また、このアルバムがバンド名義というよりプロジェクト扱いだったのに、メンバーの中にメインヴォーカリストが2名いたことも理由の一つだろう。バンドメンバーにクレジットされていたのは元Ace、SqueezeのPaul Carrack("Silent Running"、"I Get the Feeling"、"A Call to Arms")とSad Cafeにも在籍していたPaul Young("All I Need is Miracle"、Hanging by a Thread"、Take the Reins"、"Taken In")がアルバム収録曲を2分する形でヴォーカルを取る。幾分、Paul Youngの曲がハードロック寄り。演奏陣はPeter Van Hooke(ds Van Morrison等)、Adrian Lee(key Graham Bonnett等セッション多数)となっている。更にゲストヴォーカルにMike Rutherfordがプロデュースしてデビューの後押しをしたRed 7のGene Stashuckが"A Call to Arms"で、そしてJohn Kirbyなる人物が"Par Avion"、You are the One"で参加。その他にもAllan Murphy(g Kate BushやGo West等)、Derek Austin(key)、Ian Wherry(key)、John Earle(sax)、Ray Beavis(sax)、Louis Jardin(perc.)が参加。今でも全く色褪せない、このサウンドこそ、Mike Ruthefordの面目躍如、といったところだろう。このアルバムから"Silent Running"と"All I Need is Miracle"という2曲のトップテン・ヒットも出ている。"A Call to Arms"の作曲にはGenesisのPhil Collins、Tony Banksもクレジットされており、どこか当時のGenesisに通じる壮大なサウンドも聞かせる。 |
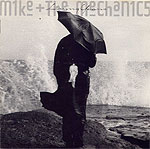 | Living Years ('88) | 前作の成功の後押しもあり、Genesisの大ヒットアルバム"Invisible Touch"で世界を席巻した後、製作された2nd。前作と全く同じスタッフを揃えて、同じフォーミュラで録音されている。但し、今作では、ゲストヴォーカリストは使わず、Paul Carrack("Nobody's Perfect"、"The Living Years"、Nobody Knows"、"Don't"、"Why Me")とPaul Young("Seeing is Believing"、"Poor Boy Down"、"Blame"、"Black & Blue"、"Beautiful Day")のみ起用。バンドとして更に強力でタイトな演奏を聞かせる完成度の高さが素晴らしい。"The Living Years"のゆっくりとチャート上り詰め、最終的にナンバーワンヒットに繋がったが、それだけのアルバムでない。全ての楽曲の完成度が高いが、どちらかといえば、アルバム中盤、"Poor Boy Down"から最後の"Why Me"にかけてが、個人的なハイライト。ハード寄りなPaul Youngとソウルフルな喉を聞かせるPaul Carrackの使い分けも良い。今回のGenesisメンバーのカメオ出演は"Black & Blue"でリフの演奏がMike RutherfordとPhil Collinsの演奏によるもの。そのリフの録音がTony Banks。また、この"Black & Blue"と"Beautiful Day"ではPaul Youngが共作者にクレジットされている。全体的に前作同様、80年代的のゴージャスに作り込まれたサウンドでありながら、今でも全く古臭く聞こえないというのは、センス以外の何物でもないのかもしれない。 |
 | Word of Mouth ('91) | 今作では、Mike Rutherfordとプロデュースと相棒を務めてきたChristopher Neilに10曲中6曲でRuss Titelmanを3人目のプロデューサーに起用(この頃のRuss Titelmanというと、Eric Claptonの復活アルバム"Journeyman"のプロデュースが印象的)。今作では、Mike RutherfordとPaul Carrackの共作曲"Get Up"から始まり、5曲目"The Way You Look at Me"と最後の"Before"で共作を行っており、今作での重要なポジションを担っている。その為、今までよりもPaul Carrackが得意とするソウル色が強いアルバムに仕上がっている。表題曲はPaul Youngが歌う擬似ライブ(Kitson Hallの観客の声援が入っている)で始まるノリの良い佳曲。その他にもPaul Youngは"Yesterday、Today、Tomorrow"(個人的に今作でのハイライト)、"Stop Baby"(初バラード?)、"Let's Pretend It didn't Happen"を担当。サポート陣はTim Renwick(g)、Steve Piggot(key)、Phil Todd(sax)、Martin Ditcham(perc.)、Pino Paladino(b)、Ian Wherry(key)といったセッション畑では有名どころが名前を連ねている。 |
 | Beggar on a Beach of Gold ('95) | まず、バンドメンバーとしてクレジットされているのがMike Rutherford(g、b、key)をはじめPaul Carrack(vo、key)、Paul Young(vo)、Peter Van Hooke(ds)とダウンサイズされ、そのほかはセッションプレイヤーで賄う、という形態を取るが、それでも相変わらずな面子を揃える。Gary Walis(ds)、Adrian Lee(key)、BA Robertson(key)、Wix(key)、Clem Clempson(g)、Andy Newmark(ds "I Believe"のみ)となっている。プロデュースにはChristopher NeilとMike Rutherfordがあたっており、従来の形へと。楽曲もBA Robertsonが13曲中4曲、Christopher Neilが5曲で共作陣に名を連ねる。そして、今作でキーとなるのが2曲のカバー曲。Smokey Robinsonによるヒット曲"You've Really Got Hold on Me"とStevie Wonderの"I Believe (When I Fall in Love It will be Forever)"("Talking Book"に収録)。狙ったのだろうが、両者ともにモータウンソングである。そして、Paul Carrackが"Over My Sholder"と"Web of Lies"のソングライティングに参加しているのも見逃せない。正直、このカバー曲2曲がこのアルバムの性質を全て物語っているだろう。ある意味、Phil Collinsのソロと近い方向性ではあるが、決して重ならない。それは、多分、Phil Collinsがシンガーとして、歌いたい曲にアプローチするのに対してMike + the Mechanicsはもっとソングライター的な視点で曲に取り組んでいるように思える。その結果がこのモータウンソング2曲なのではないのだろうか? |
 | Mike & the Mechanics ('99) | ジャケットにM6とあるのは、多分96年に出された"Hits"と題されたベスト盤を含んでのことだろう。今作では更にバンドは縮小され、Mike Rutherford(g、b)、Paul Carrack(vo、key、g、ds)、Paul Young(vo、perc)というトリオでMike & the Mechanicsとされている。そこに、前作でも参加したGary Wallis(ds)と残りはプログラマーが参加。また、プロデューサーも複数起用しており、Miker Rutherfordが"Now that You've Gone"以外全て関わっているものの、単独では冒頭の"Whenever I Stop"、"Ordinary Girl"、"If Only"の3曲のみ。その他では、Chris Neil、Nick Davis、Matthew Vaughanをパートナーに。今までの作品で聴かれたオーヴァープロデュースでゴージャスな音作りはぐっと抑えられ、シンプルな音作りに神経を注いでいる。また初めての試みとしてMike Rutherford、Paul Carrack、Paul Young3名の共作で"Ordinary Girl"、"Alwasy Listen to Your Heart"の佳曲を書下ろしており、次作への期待を高まらせた矢先、翌年00年、Paul Youngの訃報が届く。53歳という若さであり、この作品が遺作となってしまった。 |
 | Mike + the Mechanics + Paul Carrack "Rewired" ('05) | "Rewired"と題された本作の名義はMike + the Mechanics + Paul CarrackとPaul Carrack(vo、key、g)を前面に押し出し、Mike Rutherford(g、b)のパートナーとして作曲にも全曲に積極的に関わっているのが特徴だろうか。また、今作にはWill Batesが作曲に関わったデジタルなインスト"Rewired"と"Underscore"が収録されている。歌物はまるで初期に戻ったかのようなデジタルなプログラム主体のサウンドにPaul Carrackの声をふんだんにフィーチャーしたもの。"Perfect Child"などは"Living Years"の流れを汲むコーラスが美しい佳曲。"Falling"などもモダンなサウンドを取り入れたダンサンブルなナンバー。共同プロデュースにPeter Van Hooke(ds)の名前があることから、その他のIan Thomas、Neil Wilkinsonといったドラマー陣よりも貢献度が高かった、ということなんだろう。また、その他にRobbie Mckintosh(g)なども参加している。ジャケットをよく見ると1stのジャケットを加工したような作品となっていることから、やはり原点回帰のような心意気も感じる作品。因みに私が所有している盤はアメリカのRhino盤(CCCDではありません)。 |
 | The Road ('11) | 新しい編成で再出発したMike + the Mechanics。ヴォーカルにAndrew Roachford(元Roachford)とTim Howar(元Van Tramp)を迎え伝統的な編成を保つ。98年のGenesisのツアーにも同行したAnthony Drennan(g)、Pink Floydの"Delicate Sound of Thunder"などで叩いていたGary Wallis(ds、Pink FairiesのLarry Wallisの従兄弟にあたる)、Luke Juby(key 元Mika)が参加。更に南アフリカ出身のArno Carstens(元The Springbok Nude Girl)が"Background Noise"、"It Only Hurts"、"Hunt You Down"のしっとりとした3曲でリードヴォーカルを取る。その他にギターにMartin Sutton、Ben Weaver(Take Thatのツアーなどに参加)、Hugo Flower(Stereo Son)、Jamie Moses(Queen + Paul Rodgers等)、オルガンにPeter AdamsとGeorge Hewlett(Stereo Son)、キーボードにToby ChapmanとJamie Norton(Take Thatのツアー等に参加)、ドラムにHarry Rutherford(Mikeの息子 Stereo Son)を起用。Andrew Roachfordの力強いヴォーカルが印象的。時折Eric Martin辺りを思わせるフィーリングがある。この辺りはやはり故Paul Youngのイメージと重なる。"Heaven doesn't Care"は"for Neda"という副題があるように09年6月20日イラン大統領選デモで射殺されたNeda Agha-Soltanについて歌っている。プロデュースはChristopher NeilとMike Rutherfordというお馴染みのラインナップ。Mike + the Mechanicsのキャリアを俯瞰したかのような多彩な要素を散りばめたアルバム。 |
Genesis
 | "From Genesis to Revelation" ('69) | この盤は、まず、最初に68年2月に発売された"The Silent Sun"のモノ・バージョンにカップリングの"That's Me"が収められていてから本編へと入る。そして本編終了後に68年5月に出された"A Winter's Tale"とそのカップリング曲だった"One Eyed Hound"が収録されている編集盤に近い構成を持つ。Tony Banks(p)、Mike RutherfordとAnthony Phillips(g)にPeter Gabriel(vo)という編成。シングル曲ではChris Stewartというドラマーを起用しているようだ。そしてアルバムではJohn Silverにチェンジしている。プロデューサーのJonathan Kingがある程度コンセプトを提示し、バンドがそれに対して動く、という形であったようだ。ストリングアレンジにArthur Greensladeを起用し、シングルでは成功したものの、アルバムでは、ストリングスに片方のチャンネルを奪われた形となり、バンドはプロデューサーに対する不信感が増幅したようだ。アルバムには、キャッチーなサイケ・ポップナンバーが並ぶ中、唯一、ハッとさせられたのは"One Eyed Hound"のオープニングギターが丸でJimi Hendrixのようなサウンドで、こういう音を模索していたとしたら、Genesisの1stアルバムは全く違ったサウンドを出していただろう。 |
 | "Tresspass" ('70) | 正に劇的という形容詞が相応しい進化を遂げたGenesis。ドラマーをJohn Mayhewに代えのが要因ではないだろうが、そのドラミングがドラマティックなダイナミクスを生み出しているのは確か。既にシアトリカルなヴォーカルパフォーマンスの萌芽が出ていたPeter Gabrielのヴォーカルはここで一気に開花した、と言っても過言ではないだろう。そして、興味深いのはミュージシャンの武器とも言える楽器群の充実。Peter Gabrielのフルート、Anthony Phillipsのエレクトリックの他に12弦アコースティックやダルシマー、Anthony Banksのメロトロン、Michael Rutherfordの12弦アコースティックの他チェロなどを使用。プレイヤーとしての多彩なサウンドを出すことを可能にし、アレンジの可能性の幅を一気にアートロックの水準まで自分たちの手によって引き上げてしまった。静が繊細な弦楽隊であれば、対比するかのように動である楽曲のドライヴィング・フォースは、Anthony Banksのオルガンが主軸で、引っ張って行く様は圧巻である。"Stagnation"の最後の最後で出てくるフレーズは、バンドの顔とも言うべきフレーズとなる。そして続くAnthony PhillipsとMichael Rutherfordの奏でる繊細なギターの美しさにも息を呑む。Paul Whiteheadによるアートワークはよく見るとアルバム各曲のタイトルが隠れているようだ。正に新生Genesis。決して聴き逃してはいけない。 |
 | "Nursery Cryme" ('71) | Steve Hackett(g)、Phil Collins(ds)を迎えたことで所謂黄金期のラインナップがここに完成する。パッ見、幻想的なジャケットが印象的だが、女の子がクリケットのマレット(バットみたいなヤツ)で人頭を打っているというもの。タイトルの"Nursery Cryme"は童謡の意味であるNursery Rhyme(=Mother Goose)から取られたのであろう。冒頭の"The Musical Box"の歌いだしから「"Old King Cole"(有名なマザーグースの一篇)をかけて」と。そして"Old King Cole"そのものが挿入されている(「Old King Cole was a merry old soul...」というパート)。因みに"Old King Cole"はエセックス州に住んでいたケルト族の王と言われている。またジャケットにこの曲に纏わるショートストーリーが書かれている(ジャケットもそのストーリーから発展したものだろう)。繊細なヴォーカル・パフォーマンスやアコースティック・ギターから、荒れ狂うオルガンを中心とした後半のアンサンブルの見事なまでの世界観を表現できているのは、正に英国ならではのバックグラウンドの賜物だろう。続く、短くも美しい曲"For Absent Friends"ではPhil Collinsが既にリードヴォーカルを取っているのに驚く。"The Fountain of Salmacis"は勿論ギリシャ神話から。正に神話の世界に迷い込んだの如くの美しいサウンドが印象的。その他にも"Harold the Barrel"(ビール腹のハロルド?)あたりも何かしら下敷きになっているストーリーがありそう。牧歌的で英国的で、島国が持つ猥雑さもある。聴けば聴くほど発見がある作品。 |
 | "Foxtrot" ('72) | 前作と同じラインナップで製作された作品。荘厳なメロトロンによって導かれるオープニングを持つ名曲"Watcher of the Skies"のタイトルはJohn Keatsの「チャップマン訳ホメロスを初めて読みて」から拝借されているとも言われているが、歌詞の中身はArthur C.Clarkeによる「幼年期の終り」を題材にしている。このロックバンドにしては異常なまでの気位の高さは何なんだろう?Mike Rutherfordのベースラインが印象的。シアトリカルな"Get'em Out by Friday"はまんまというか、住宅問題を赤裸々に描いた政治色の濃いもの。"Can-Utility and the Coasterliners"はクヌーズ1世の伝説をベースにしている。Steve Hackett奏でる"Horizons"はバッハの無伴奏チェロ組曲第1番プレリュードの改作(?)。そして、23分近い大作"Supper's Ready"へと続く。「夕食が出来ました」というバトラーかメイドが主人にでも言うかのような台詞のようなタイトルも珍妙ではあるが、歌詞も結構支離滅裂というか脈絡がない引用が多い。Steve Hackettらしいソロや勇壮なTony Banksのオルガン・サウンドに彩られるエジプト王のイクナトン("Ikhnaton and Itsacon and Their Band of Merry Men")が出てきたら、しっとりとナルシス("How Dare I be So Beautiful?")を歌うPeter Gabrielは"Willow Farm"では駄洒落に近い言葉遊びに興じるコミカルな曲を演出する。一転して緊張感を増していく黙示録をテーマにした"Apocalypse in 9/8"から最後の"As sure as Eggs is Eggs"(因みにタイトルは「明快な」の意の慣用句)でも黙示録19章17節からの引用がある。故に"Supper's Ready"。 |
 | "Selling England by the Pound" ('73) | まるで民族伝承歌のようなフォーキーな歌いだしから、英国が持つ歴史の雄大さを感じさせる"Dancing with the Moonlit Knight"は徐々にTony BanksとSteve Hackettのスピーディーなプレイと共に攻撃性が増していく様は圧巻であり、また違ったGenesisの魅力を伝えてくれる。この曲でのSteve HackettのプレイはどこかYesのSteve Howeを意識したようなプレイにも聴こえる(そう考えると後のGTRはなるべくしてなったアイディアかもしれない)。但し、このロマンティシズム溢れる曲に対して、その歌詞はシニカルでモダンなレファレンスを持つ。例えば、Wimpy(ハンバーガーチェーン店)やGreen Shield stamp(一個買うと一個おまけがつけますよ戦略の走りと言われている)等。続く"I Know what I Like"はジャケットに基づいた歌詞と書かれているが、ジャケットはBetty Swanwickの"The Dream"という絵。但し、ジャケットの芝刈り機は歌詞にあわせるために後から付け足された。この曲でもPeter Gabrielのお得意のストーリーテリングを堪能出来る。そしてGenesisのキャリアの中でも最も大切な曲の一つ"Firth of Fifth"のクラシカルなオープニング、力強いPeter Gabrielのヴォーカル・プレゼンテーションにフルート・ソロも秀逸。Phil Collinsがリードを取る第2弾"More Fool Me"からPeter Gabrielが2人のキャラクターを演じ分ける"The Battle of Epping Forest"、そして美しいインストの小曲はバンド内部でも今作に入れるか入れないかでモメたらしい。個人的にはこの小曲が良い大作の間に入るインタールード的な役割を果たしているので、ちょうど良かったんだけど。そして、このアルバムを象徴するようなロマンティシズム溢れる"The Cinema Show"はT.S.Eliot(ミュージカル「キャッツ」の元を書いた人で有名)の"The Waste Land"(邦題「荒野」)からインスパイアーされたもの。その歌詞は結構セクシャルでちょっと驚く。Genesis流シニカルでニヒルなロマンティシズムの結晶。 |
 | "The Lamb Lies Down on Broadway" ('74) | ついに、というか、Peter Gabrielの演劇性や詩世界が思い切り前面に打ち出された感があるコンセプト作品。ストーリーはRaelというプエルトリカンが兄Johnを捜し求める中、奇妙な困難に遭いながら、兄を探す、というものだが、その実、Raelが探しているのは失われた自分自身の一部、というもの。そんな自己探求というテーマを持ったもの。本作は舞台がNew York City。この作品のドライヴィング・フォースは正しくPeter Gabrielのヴォーカル・パフォーマンスに他ならない。その声だけでシアトリカな声で多彩な表情を見せるが、舞台が舞台だけに時にBob Dylanのように聴こえる(Bob Dylanも相当声を作る人らしい)場面もある。オープニングの"The Lamb Lies Down on Broadway"のサビはThe Driftersの"On Broadway"を思わせたり、"In the Cage"のオープニング・ラインがThe Temptationsの"My Girl"だったりとR&Bからの影響も見受けられる。この頃のコンセプト作の性で、インスト曲の挿入というのがある。物語の進行上どうしても入れなくてはいけなかったり、したり、しなかったり。今作でも"Back in N.Y.C"の後の雄大な"Hairless Heart"のサウンドや混沌したアヴァンギャルドでSteve Hackettの破天荒ぶりが聴ける"The Waiting Room"。"Silent Sorrow in Empty Boats"や"Ravine"と言った曲でもある意味、Genesisらしからぬサウンドスケープが聴ける。こういった曲はEnoが"Enossification"でクレジットされている事からインプットの出自も判るというものだろう。"The Colony of Slipperman"の"The Raven"でのJohnパートはPhil Collinsがリードヴォーカルを担当している。今作は難解とレッテルが貼られる事が多い作品ではあるが、表題曲を始め、"In the Cage"、カヴァーされる事が多い"Back in N.Y.C."、美しいメロディーを持つ"Carpet Crawlers"、"Lillywhite Lilith"等、名曲も多いので、臆せず楽しんで欲しい作品。因みに本作を最後に家庭の問題もありPeter GabrielはGenesisを脱退する。 |
 | "A Trick of the Tail" ('76) | Peter Gabrielが脱退し、一説には400人ものシンガーをオーディションしたとか?その事からもPhil Collins(ds)がヴォーカルを兼任するのを嫌がったのも想像に難くない。既に楽曲は出来上がっており、Phil Collinsが"Squnok"を歌った時に、残りの曲も全てPhil Collinsが歌うべきだ、と決まったそうだ。寓話的なジャケットから、前作のシュールリアリズムな作風から本来の作風に戻ってきた、と言えるだろう。それは何もジャケットのみならず、サウンドも同様。Steve HackettやMike Rutherfordの弦やTony Banksの飽くまでも英国的な香りを漂わせるキーボード群のたゆたうサウンド。以前かリードは取ってはいたPhil Collinsも、このスタジオ作ではPeter Gabrielの穴を十分に埋めていると言えるだろう。"Dance on a Volcano"の力強さ、"Mad Man Moon"や"Ripples"の叙情性等も素晴らしいが、個人的には何よりも表題曲のビートリーなメロディーの美しさにやられる。今作の最後には後々ライブナンバーとしてその地位を確固たるものとする"Los Endos"。イントロは"It's Yourself"(シングル"Ripples"のB面)からの取られており、"Dance on a Volcano"や"Ripples"のテーマが繰り返される構成となっている。そして、最後の最後のフェードアウトの所で「There's an angel standing in the sun…」と"As Sure as Eggs is Eggs"の歌詞が歌われている。"Los Endos"のアレンジはPhil Collinsが担当している。 |
 | "Wind & Wuthering" ('76) | 前作から10ヵ月後という短いインターバルで出されたモノトーンのアートワークが印象的なアルバム(個人的にはGenesis作の中で最も好きなアートワーク)。アルバム・タイトルからしてエミリー・ブロンテの「嵐が丘」からの影響が伺えるのは明白。全体的にPhil Collinsのヴォーカルにかかるエコーや裏声が気になる。この辺りは、後のEarth Wind & FireのヴォーカリストPhilip Baileyとのデュエット曲"Easy Lovers"をも既に思い出させるし、アーバン・ソウルなどMotownあたりへの憧憬が聴こえるような気もする。冒頭の"Eleventh Earl of Mar"は22nd Earl of Marとも呼ばれるJohn Erskineをモチーフにした曲。美しいGenesisらしいインスト曲"Wot Gorilla?"はツアー・ドラマーであるChester Thompsonを指しているらしい。クラシカルなギターに導かれる"Blood on the Rooftops"のイントロはSteve Hackettの真骨頂であろう。後半、クラシカルな雰囲気を引き継いだヴォーカルパートも良い。そして、アルバム・タイトルと密接な繋がりを持つインスト2曲"Unquiet Slumbers for the Sleepers…"と"… In That Quiet Earth"は嵐が丘最後の1文「wondered how anyone could ever imagine unquiet slumbers for the sleeps in that quiet earth」から。インスト・パートの充実とメロディーの素晴らしさは流石。 |
 | ... And Then There were Three... ('78) | アガサ・クリスティーよろしくな「そして3人が残った」という名のアルバムはタイトル通りSteve Hackettが脱退後、Phil Collins(ds、vo)、Tony Banks(key)、Mike Rutherford(g、b)で作り上げた作品。複雑なリズムを刻むオープニングを持つ"Down and Out"の歌詞はどこかシニカルで、聴き手を励ますような、皮肉っぽくも示唆的な感じ。初期Genesis的な静を持つダイナミックな名バラード"Undertow"から活き活きとした"Ballad of Big"の後半部や続くメロディーが美しい"Snowbound"と勢いがある。"Scenes from a Night's Dream"の人懐こいメロディーはアニメ映画「ニモ」(1989年公開)の原作「リトル・ニモ」を題材にしたもの。続く"Say It's Alright Joe"はアル中を題材にしている。こういったファンタジックな内容であれ、社会風刺を持った曲であれ、ストーリーテラーとしてのGenesisはしっかりと受け継がれている。Tony Banksのキーボード・サウンドは重厚なサウンドから煌びやかさを持つ優美な印象を持つ。特に"The Lady Lies"で聴けるソロは秀逸。後のポップなサウンドと初期のサウンドの絶妙なブレンド具合、と言えるだろう。 |
 | Duke ('80) | Mike Rutherfordは1stソロ"Smallcreep's Day"をTony Banksは"A Curious Feeling"を発表。Phil Collinsも"Face Value"のデモ作り等を行った後、本作の制作に取り掛かる。本作では80年代に突入したのを如実に表すようにサウンドが一気に垢抜け、ポップ・バンドとしての新しいサウンド・アイデンティティーを持ったGenesisを披露することに成功する。そういったサウンドは"Duchess"のドラム・マシーンの使用等に顕著と言えるだろう。オープニング・トラック"Behind the Lines"は非常に興味深いトラック。まずは、長尺なイントロでバンドの本来の持ち味を披露するも、ホーン系のシンセはファンキーな響きを持ち、その流れはそのままPhil Collinsのヴォーカル面にも表れている。後にこの曲はPhil Collinsのソロ"Face Value"にも収められる。Mike Rutherford作の"Man of Our Times"等はある種過渡期的なサウンドなのかもしれないが、これも一つのこの時期Genesisにしか出せなかった音かもしれない。Tony Banks作の"Heathaze"や"Cul-De-Sac"はモロに70年代的な作風。特に"Cul-De-Sac"の前半の情景は素晴らしいの一言。名曲"Turn It On Again"はライブでメドレーで演奏される事が多くショーのハイライト的に使われる。そして、このアルバムを締め括るのがDukes組曲である計10分以上になる"Duke's Travel"と"Duke's End"。本作のバランス感覚は非常に絶妙。 |
 | Abacab ('81) | 前作で見せたポップ・センスを更に推し進めた作品。オープニングの表題曲は時代を感じさせるデジ・ロック。そして、ある意味、この時期のGenesisを顕著に代表するのがEarth Wind & Fireのホーン・セクションを迎えたダンサンブルなポップ・チューン"No Reply at All"。レゲエなリズムを持つ"Me and Sarah Jane"(ちょっと意外ながらTony Banksによる曲)、どことなく進行が70年代のGenesisを思わせる"Keep It Dark"、大仰なオープニングを持つ"Dodo / Lurker"は往年のファンを喜ばせる唯一のトラックかもしれない。パンク/ニューウェーブを通過したトラック"Who Dunnit?"に後のPhil Collinsらしいバラードの典型とも呼べる"Man on the Corner"(Phil Collins単独で書いた曲)、そしてMike Rutherfordが書いた"Like It or Not"、落ちぶれたロック・スターの悲哀を歌った曲で最後を締める構成。今作での最も特徴的なのはPhil Collinsの多様な曲を歌いこなす歌唱力のアップだろう。 |
 | Genesis ('83) | 前作でエンジニアを務めたHugh Padghamを共同プロデューサーに迎えた作品。ドラム・マシーンをアルバム全体で使用されている。オープニング・ソング"Mama"はPhil Collinsのシアトリカルで力強いヴォーカル・パフォーマンスが素晴らしい。"Home by the Sea"は幽霊館に忍び込んでしまった泥棒の話。そして6分強の"Second Home by the Sea"へと繋がっていく。違法滞在している外国人を揶揄する"Illegal Alien"はそのテーマに反して曲調はヤケッパチで明るくお気楽なムードさえ漂わせているのがGenesis流というところだろうか。ホーン系のシンセを使いファンキーな路線を持たせてもGenesisの持つヨーロピアンな所が抜けない力強いナンバー"Just a Job to Do"からGenesisらしい大仰な"Silver Rainbow"、テープの逆回転のようなサウンドをバックグラウンドに持つ"It's gonna Get Better"の最後3曲の畳み込みは秀逸。80年代的なサウンドではあるのだけど、現在でも全く色褪せていないサウンド・プロダクションは素晴らしい。 |
 | Invisible Touch ('86) | 英国ではヒットチャート1位を記録しただけでなく96週に渡ってチャートに残り、このアルバムから切られたシングルも表題曲のみならず、"Anything She Does"、"Domino"、"In Too Deep"、"Land of Confusion"、"Throwing It All Away"、"Tonight、Tonight、Tonight"とアルバム最後を飾るインスト曲"The Brazilian"を除く全ての曲がシングルとしてリリースされた名実共にモンスター・アルバムとなり、Genesisという名を世界中の老若男女に知らしめた傑作ポップ・ロック・アルバム。英国の人形劇「スピッティング・イメージ」の人形を使ったPVが好評だった"Land of Confusion"、Genesisのプレイヤー・サイドを強く印象付ける10分以上の2部構成になっている"Domino"と80年代中期を代表するサウンドがギッシリと詰め込まれた作品。Hugh Padghamを迎えたプロダクションは現在でも全く色褪せず、時代を超えた作品と言えるかもしれない。Genesisの80年代を総括するかのような作品。Genesisのみならず、ロックシーンにとっても大切な重要作であることはまず間違いない。 |
 | We can't Dance ('91) | たっぷりと5年かけ精力的に前作のプロモーションを行った後のアルバム。本作もまたチャートに長い時間残った作品で、メジャーでのGenesisの勢いが衰えていない事を証明した作品。"No Son of Mine"や"I can't Dance"等ちょっとブルージーなサウンドを取り入れているのは確かにこの頃のトレンドだったような気がする。"Jesus He Knows Me"はこの頃全米を席巻していたTV宣教師を皮肉った内容の歌詞。"Since I Lost You"は盟友Eric Claptonの亡くなった息子のためにPhil Collinsが歌詞を書いた曲。大曲"Driving the Last Spike"のドラマティックな構成は流石。本作もまた上質なポップ・アルバム。 |
 | Calling All Stations ('97) | 96年にPhil Collinsが脱退を表明。後任にStiltskinのRay Wilsonを起用。ドラムに様々なセッションで活躍していたNir ZidkyahuとNick D'Virgilio(4曲のみ)が担当。Ray Wilsonは時にBryan Adamsを思わせるブルージーな喉を持っており(特に"Not about Us"のようなバラード調の曲に顕著)、オープニングの表題曲などは若返った印象を受ける。"Congo"はGenesisとしては初めてのアフリカン・リズムを取り入れた曲。"The Dividing Line"の前半のNir Zidkyahuのドラミングも聴き所の一つ。確かにヴォーカリストの交代、というバンドの顔が変わったにも関わらず、Genesisのサウンドという面では恐ろしく変化がない。それだけTony Banks、Mike Rutherfordのサウンドが強力、ということなのだろう。実質、本作がGenesisのラスト・スタジオ作となっている。 |
Others
 | Steve Hakcett "Voyage of the Acolyte" ('75) | Genesis在籍中に発表されたSteve Hackettによるソロ・デビュー作。タロットカードをモチーフにした作品となっている。繊細さと万華鏡のように表情を変えるサウンドの対比が素晴らしい。コア・メンバーに弟のJohn Hackett(flute、synthesizer、bell)とJohn Acock(elka rhapsody、mellotron、harmonium、piano)を揃え、GenesisからMike Rutherford("Shadow of the Hierophant"を共作)とPhil Collins("Star of Sirius"でリードヴォーカルを取る)が参加。その他にSally Oldfieldが"Shadow of the Hierophant"のヴォーカルを担当、Robin Miller(oboe等)、Nigel Warren-Green(cello)やPercy Jones(b)、Johnny Gustafson(b)の名前も見える。出てくるサウンドは非常にGenesisのメンバーらしい作品、と言えるだろう。05年再発時に"Ace of Wands"のライブと"Shadow of the Hierophant"のロング・ヴァージョンがボーナストラックとなっている。 |
 | Anthony Phillips "The Geese and the Ghost" ('77) | アコースティック・ギターの繊細さ、雄大なストリングスをはじめとするオーケストレーション。ちょっとしたサイケがかったギミック。どこまでも英国的なサウンド、というのだろう。Mike Rutherfordは"Henry: Portraits of Tudor Times"と表題曲である"The Geese and the Ghost"と"Chinese Mushroom Cloud"を共作した他、ほぼ全面的にサポート。Genesis関連ではPhil Collinsが"Which Way the Wind Blows"と"God If I Saw Her Now"で、このアルバムらしい温雅な声を披露している。後者では元Principal Edwards Magic TheatreのViv McCauliffeの儚げな声も聴ける。Steve Hackettの弟John Hackett(flute)やJack Lancaster(flute、lyricon)、Tom Newman(hecklephone、bulk eraser)等見慣れた名前も参加している。また08年再発時にはデモやベーシック・トラックやGenesisの元ドラマーJohn Silverに捧げられたシングル予定曲だった"Silver Song"(Phil Collinsがヴォーカルとドラムを担当)が収められたディスクが入った2枚組仕様となった。傑作と呼ぶに相応しい名盤。 |
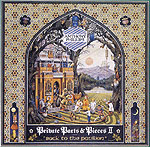 | Anthony Phillips "Private Parts & Pieces II Back to the Pavilion" ('80) | 5つのパートからなる"Scottish Suite"組曲でMike Rutherfordがベースで参加。この組曲には「スコットランドのサケ漁に従事する人のための歌と12世紀パラグアイでスズの炭鉱で働いていた人への悲歌を集めたもの」という妙な副題が付いている。"The Geese and the Ghost"の"Henry"のテーマ部と被る部分もあるようだが、。残りは9分近い"K2"を含む小曲集。テープの逆回転を使った"Romany's Aria"などのトリッキーなトラックもある。牧歌的なAnthony Phillipsの魅力をたっぷりと味わえる作品集となっている。ドラムは全編通してAndy McCullochが担当。 |
Sad Cafe
 | Politics of Existing ('85) Whatever It Takes ('89) | ジャケットは00年に出された"Saving Grace"と題された両作を収めた2CD再発盤。前者では、Paul Young(vo)を始め、Ian Wilson(g)にMike RutherfordとNico Ramsdenがリードギターを担当。Des Tong(b)、Jeff Seopardi(ds)、Danny Schogger(key)を担当。"Heart"と"Keep Us Together"のみMike Hehir(g)、Vic Emerson(key)、Lenni(sax)とDave Irving(ds)というSad Cafe本来の布陣で収録されている。Mike + the Mechanicsとの絡みで82年から録音が始まっていたが、85年まで日の目を見ることはなかった。新生Sad Cafeとして多彩な音楽性を併せ持つアルバムを発表。Vic Emersonも3曲で作曲には関わる。レゲエ調のそのものずばりな"Refugees"はドラマーのJeff Seopardiによるもの。更に"Heart"はSue Quinnの曲。"Whatever It Takes"の方ではMike Hehirが復帰。Steve Pigott(key)とPaul Burgess(ds)が新しく加入し、Ian Wilson、Des Tong、Lenniというラインナップになる。今作でも、上質な英国ポップロックとしか形容のしようがない作品を提供する。"So Cold"はSteve Pigottの曲。"I won't Leave"は"Don't Walk Out on Me"ともクレジットされているが、全く同じ曲。両作とも、常にメインとなるのは当然の事ながら、Paul Youngのソウルフルなフィーリングを持ったヴォーカル。その魅力は現在でも十分魅力的だ。R.I.P. |
 | Paul Young "Chrnoicles" ('11) | 00年7月15日に亡くなったPaul Youngの未発表曲集。本作はプロデューサーAlistair GordonとMartin Kronlundによって纏められたよう。Mike Rutherford(g)は力強いソロを入れたPau Youngと共作したパワーバラード"Your Shoes"で客演。Mike and the Mechanicsの盟友Paul Carrack(organも担当)とのデュエットが聴ける"Grace of God"(Eric Stewartがkeyとgで参加)の繊細さなポップチューンや、Victor Emerson(Sad Cafe)がストリング・アレンジなどを手掛けた叙情的な"Water Now the Seed"、10ccのGraham Gouldman(g、b)とSteve Pigott(program)がバックアップした"I'm in Heaven Again"などが収められている。ボーナス・トラックにMike + the MechanicsによるSad Cafeのヒット曲"Every Day Hurts"のアコースティック・ライブを収録。その他にもMartin Kronlundのヘヴィーなギターが鳴る"Loss of Innocence"や"Here Comes the Future"、Michael Byron-Hehir(Barclay James Harvest、Sad Cafe)、Ashley Mulford(Sad Cafe)、Martin Kronlundという3人のギタリストを擁した"Two Wrongs"などもある。Paul Young縁のある10ccやMandalaband、Sad Cafeの名手たちが一堂に会した極上のアルバム。Paul Youngの名前を冠するに相応しいアルバム。 |