
"Night in Amnesia" ('95)

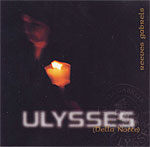

Reeves Gabrels
David Bowieの片腕で済ませて良いのか?David Bowieの特集をする時でさえ、無視されることがあるのは絶対におかしい。
 |
David Tronzo / Reeves Gabrels "Night in Amnesia" ('95) |
Knitting Factory関連などで名前を見ることが多いDavid Tronzo(g)との実験色の強いコラボレーション作。Matthew Gruenberg(b)、Mike Levesque(ds)を中心にBilly Conway(perc.)、Jay Bellerose(perc.)などのセッション畑のプレイヤー達を迎えて製作されている。大半は、リズム隊を含めてた曲が占めるが、"Something is Dead in the Cellar"、"Not gonna Happen"、"Two Memories of the Same Event"といった曲ではギタリスト2人のみによる曲も用意されている。非常に多彩なサウンドを聞かせるアルバム。奇妙なノイズを散りばめた浮遊感のある曲や、アコースティックの特性を活かした曲など。特に琴のような音を出す"Ballad of a Man Long Gone"などは東洋嗜好的なものも感じる。そういう意味でも、やはり聴き所は、Reeves GabrelsとDavid Tronzo2人のギターワーク。スライドやドブロをメインに使うDavid Tronzoと浮遊感漂うノイズを奏でるReeves Gabrelsの対比が面白い。オールインスト作品。ガレスピーの"A Night in Tunisia"のカバー入り(これがまた…)。 |
 |
The Sacred Squall of Now ('95) | ある意味Reeves Gabrelsだからこそ作り得た作品。ポップでちょっと捻くれたアーティーなグラムロックに、ノイジーなインスト群、3曲("Hushu"、"Thirteen"、"Firedome")。オリエンタル趣味を醸し出す"Hushu"や単調なオーケストレーションの響きが印象的な"Thirteen"。そしてハードに攻める"Firedome"とインスト群の出来が良い。アルバムは、まずはPixiesのFrank Blackがvo参加の"119 Years Ago"(どちらかというとDavid Bowieの方が似合いそうなんだけど)から始まる。David Bowieは"You've been Around"(David Bowieの"Black Ties and White Noise"と同曲、別アレンジ)と"The King of Stamford Hill"で参加。"You've been Around"は"Black Ties and White Noise"ではテクノっぽくメカニカルで、トランペットの響きがアヴァンギャルドな仕上がりなのに対して、こちらはストレートなハードロック的な出来になっている。正しくグラムロックといった感がある。この曲の両者の対比が正しくアーティストカラーを思い切り出している、象徴的な曲かもしれない。映画"Sid and Nancy"にも出演していたGary Oldmanも"You've been Around"に参加。"B.N.Y."にJeffrey Gainesが参加。最後を締めくくるのはCharlie Sextonを迎えてのCreedence Clearwater Revivalのカヴァー"Bad Moon Rising"。それ以外では、Reeves Gabrelsがvoを取っている。クレジットにロック界では珍しくない"No Keyboards、Synthesizers or Vibrators"のクレジットが…。 |
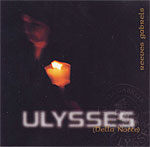 |
Ulysses (Della Notte) ('00) | 当初は99年にMP3.comでダウンロード販売されていたものに"Trap"と"Yesterday's Gone"を足して発売されたCD盤。サウンドとしては、やはりDavid Bowieの"Earthling"のフォローアップという感じ。ノイジーでありながら、キャッチーなサウンド・ギミックに覆われているアルバム。"Earthling"ほどの捻くれ度合いもなく、ハードロック的な出自が明確に打ち出されている。そして、グラムが持っていた「しなやかさ」がここにある。前作から引き続き参加のDavid BowieとFrank BlackがドラムとヴォーカルにDave Grohl(Foo Fighters)を向かえ"Jewel"(作曲はReeves GabrelsにFrank Black、David BowieとMark Plati)に参加。期待を裏切らない想像通りの音が出てくる。Robert Smith(The Cure)とJason Miller(Godhead)が"Yesterday's Gone"にヴォーカルで参加。この曲ではRobert Smithは全面的に作曲、インストパート等も協力しており、単なるゲストヴォーカリストなどではなく、パートナーシップが結実した名曲。 |
 |
Rockonica ('04) | Steve Vaiが主催するレーベルFavored Nationsから。とはいえ、インスト物のはずもなく、"13th Hour"と題されたインスト以外はReeves Gabrielがしっかりと歌っている。基本はこのアルバム製作以前よりライブなどで活動を共にしているPaul Ill(b)とBorck Avery(ds)のトリオで、その殆どがこのトリオを基本とした編成。そこにElroy McMullen(lap steel等)、Matt Resnicoff(g)、Donnacha O'Donnell(g)等が加わる。またDoug Lunn(b)、Ronnie Ciago(ds)のリズムセクションでも"Underneath"と"Anywhere (She Is)"を収録。スタイリッシュでありながら、時代に流されない力強いアルバム、という印象。敢えてタイプ分けをするなら、矢張りグラムなんだろう。ハードロックという程ブルージーになれず、ポップロックというには、重い。かといって、スリージーなロックンロールタイプのものでもない。正にReeves Gabrels流のスタイリッシュなハードロック、としか言いようがないんだな…。プロデュースは、こちらも一緒にライブをやるJohn Xと共同プロデュース。因みに冒頭の"Sign from God"はRobert Smithとの共作曲(今回はRobert Smithの参加はナシですが)。 |
David Bowie
 |
Tin Machine "Tin Machine" ('89) | David Bowieファンにはすこぶる評判の悪いらしいTin Machine。曰く、「今さら、あなたがやらなくても…」的な批評が多かったようだ。よく知らないけど。でも、Reeves Gabrelsファンにはマストである(いるのかいないのか知らないけど…)。Todd RundgrenやIggy Popとの共演経験を持つHunt、Tony Salesのリズム隊兄弟にKevin Armstrongがリズムギターとハモンドオルガンで参加。キーボードでなくて、あくまでもハモンド、という所に、このアルバムのサウンドの意図が汲み取れる。タイトなリズムにDavid Bowieの素直なヴォーカル、非常にトリッキーなサウンドを出すReeves Gabrels。David Bowieが一人で書いた"Crack City"には70's的な自身へのオマージュ的なものも感じられる。パンキッシュというより、ビートっぽい香りが漂う"Under the God"(グルーヴのせいかな?)。そして、John Lennonのカバー"Working Class Hero"(重い…)。ファスト・ロック・チューン"Sacrifice Yourself"から面白いグルーヴを持つ"Baby can Dance"への纏め上げは最高に素晴らしい。 |
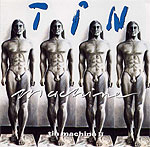 |
Tin Machine "Tin Machine II" ('91) | 前作と同じラインナップ、製作陣で臨んだ2nd。但し印象的なコーラス・パートを持つキャッチーな"One Shot"のみHugh Padghamのプロデュース。Roxy Musicの"If There is Something"を含む。モロにブルーズな"Stateside"とHunt Sales作の"Sorry"ではHunt Salesがリードヴォーカルを担当。敢えて書くが、これはDavid Bowieが組閣した「バンド」なので、これも当然と言えば当然。David Bowieファンには"You Belong in Rock N' Roll"で溜飲が下がるだろう。今作でも、ノイジーなサウンドを突きつけるReeves Gabrelsのプレイが光る。バリ島の地名から取った"Amlapura"のアコースティックを主体としたドリーミーな曲に絡むノイズや伸びやかなソロは必聴。今作で唯一David Bowieが一人で書き上げた"A Big Hurt"に勢いをつけたのは間違いなくReeves Gabrelsの咆哮ギターだろう。因みに米盤のジャケットはナニがスクラッチされて消されており(そっちの方が痛々しいよ)、その他の国では普通に出たと思う。 |
 |
"Black Tie White Noise" ('93) | Nile RodgersをパートナーにDavid Bowieが帰ってきた。何よりも今作の肝は管のような気がする。オープニングのインスト・ナンバー"The Wedding"に自らサックスを吹き込み、随所にLester Bowie(Art Ensemble of Chicago)のトランペットがDaivd Bowieの声に隣に寄り添うように鳴っているのが印象的だ。しかも"Looking for Lester"という素晴らしい曲まで用意してある。表題曲ではAl B.Sure!を迎えたR&Bやジャジーなフィーリングを持たせたり、"Jump They Say"でのファンキーなフィーリングも特徴だろう。今作のもう一つの目玉はカヴァー曲の数々だろう。盟友Mick Ronson(g)を迎えたCreamの"I Feel Free"をモダンでダンサンブルに仕上げたバージョンやThe Walker Brothersのヒット曲"Nite Flights"、モーリタニア出身のTahraが書いた"Don’t Let Me Down & Down"(オリジナル歌詞はアラビア語だったという)のカヴァーに"Rock and Roll Suicide"のアンサーソングと言われるMorrisseyの"I Know It’s gonna Happen Someday"の4曲が用意された。日本盤には"Jump They Say"と"Pallas Athena"のオルタネート・バージョンと"Lucy can’t Dance"の3曲がボーナスとして収録された。Reeves Gabrelsは後に自身のソロにも収録する"You’ve been Around"にのみ参加。"They Say Jump"でのファンキーさと対照的にDavid Bowieのサックスの音が悲しげに鳴っているように聴こえるのは気のせいだろうか。 |
 |
"1. Outside The Diary of Nathan Adler or the Art-Ritual Murder of Baby Grace Blue A non-linear Gothic Drama Hyper-cycle" ('95) |
当初は5部作の内の1作目として登場した本作(ゆえに「1」とあるのだろう)はベルリン時代のEnoを共同プロデューサーに迎えたコンセプト作。ストーリーは殺人をアートして表現するような1999年。14歳のBaby Graceが四肢に16本もの注射針を打ち込まれ、血液は全て抜き取られている死体現場からNathan Adlerの物語は始まる、というサイバーパンク調のもの。それに合わせるかのようにReeves Gabrelsのギターはノイジーで、トリッキー。曲の中にモダン・ジャズっぽい印象的なフレーズを入れるのが長けているMike Garsonのグランド・ピアノのサウンドが一層、サウンドを超現実的な世界へと誘う。Erdal Kizilcay(b)とSterling Campbell(ds)のリズム隊はノイジーでインダストリアルに影響されたリズムを叩き出す。この時点で"Hallo Spaceboy"などでドラムンベース的な高速ビートも披露されている。全19曲のうち、オープニングと5つの小さなセグエが織り込まれている。表題曲の"Outside"にはKevin Armstrongが共作者としてクレジットされており、また"Thru' These Architects Eyes"でギターで参加。この新しいNathan Adlerというキャラクターや、サウンド設定も、ある種Reeves Gabrelsがいてこそのサウンドではないかと思う。"Hallo Spaceboy"はPet Shop Boysの手によるリミックス・バージョンも出され、そこではギターは極力省かれ、テンポを遅くしたユーロビートな仕上がりにしてあった。また、"The Hearts Filthy Lesson"は映画「SE7EN」にも使われた(怖いし…)。そして、アルバム最後を締め括る"Strangers When We Meet"のリズムはThe Spencer Davis Groupの"Gimme Some Lovin'"を彷彿させる。こういうった前衛とオールディーズな組合せがDavid Bowieの真骨頂でもあるだろう。本作発表後、David BowieはNine Ince Nailsとダブル・ヘッドライナー・ツアーを行う。 |
 |
"Earthling" ('97) | David Bowie(vo、g、sax、key)に共同プロデュースを行っているReeves Gabrels(synth、g、vo)とMark Plati(key等)にMike Garson(key、p)、Gail Ann Dorsey(b、vo)とZachary Alford(ds)というバンド体制な布陣で収録している。今作は前作のサウンドを更に一歩推し進めた感があるハード&ヘヴィーな内容。結果、David Bowieのカタログ中、最もヘヴィーなサウンドを出すアルバムとなっているのではないだろうか?そこいらの下手なハードロックバンドよりもずっとエキサイティングなサウンドに仕上がっている。トリッキーなReeves Gabrelsのサウンドにジャジーなピアノを入れるMike Garson、そして肌理が細かくヘヴィーなZachary AlfordのドラムとGail Ann Dorseyのベースの疾走感が堪らない。またGail Ann Dorseyのバックヴォーカルも良いアクセントを曲に与えている。Reeves Gabrelsは"Telling Lies"と"I'm Afraid of Americans"以外全ての作曲に参加。アルバムの骨格の形成に貢献している。"Seven Years in Tibet"は中国語ヴァージョンもあるよう。名曲"Dead Man Walking"のオープニングは"The Superman"を彷彿させるリフを使用。ドラムンベース等の新しいサウンドに挑戦しつつも過去との繋がりを打ち出すところも、David Bowieらしい。David Bowieファンにはどういった反応があったのかは判らないが、ハード・ロック・ファンは必聴盤の名盤。翌年97年1月には50歳を迎えたDavid BowieはMadison Square Gardenにて多くのバンドをゲストにバースディー・ライブを行う。ヴィデオ・シューティングもされていたけど、リリースはされないのでしょうかね? |
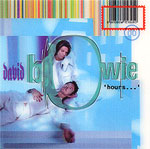 |
"hours..." ('99) | まずは、2人のDavid Bowieのジャケットに目が行く。虚ろな目で横たわるEarthling時代っぽいDavid Bowieを膝に乗せて見つめる現在のDavid Bowie。そんなジャケットを象徴するかのようにここ2作にあったような激しさは後退し、サウンドも装飾もストリップ・ダウンさせている。但し、このアルバムはちょっと変則的で"Thursday Child"、"Something in the Air"、"Seven"、"New Angels of Promise"、"The Dreamers"の5曲と日本盤ボーナス・トラック"We All Go Through"はヴィデオ・ゲーム「Omikron - The Nomad Soul」で既出。また"What's Really Happening?"はDavid Bowieのオフィシャル・サイトで行われた歌詞コンペで優勝した歌詞作品が使われている。"hours..."というアルバム・タイトルが示すように、歌詞も基本的に時間を主題に歌った物が多いように感じる。曜日を数える"Thursday's Child"、時間という試練に挑むように聴こえる"Survive"、"I got seven days to live"と地に足が着いたように歌う"Seven"、"Take us to the edge of time"と歌うのは"New Angels of Promise"等が挙げられる。前作を踏襲するかのようにReeves Gabrelsのギターが吼える"The Pretty Things are going to Hell"は映画「Stigmata」に使われた。東洋的な(というか琴と笛っぽい)サウンドに包まれたインスト"Brilliant Adventure"も挿入されている。Reeves Gabrelsは共同プロデューサーとして楽曲にも全てに関わっている。確かに全体的にメローな印象は受けるが、メロディーや曲の質感はやはりReeves GabrelsとDavid Bowieのコラボレーションそのもの、といった趣。 |
Others
 |
Too Happy "Too Happy" ('88) |
Reeves Gabrelsが参加したポップロックプロジェクト。現在はプロデューサーとして活躍しているTom Dube(vo)とセッションを多数こなしているHal Cragin(b)とClark Goodpaster(ds)からなるバンド。ハードロックほどハードではないが、時折、Reeves Gabrelsのギターが唸りをあげる場面もある。近いところだと、XTCだろうか。多彩なロックソングを聴かせる。時にカントリーっぽいフレーヴァーが聴こえる。Tom Dubeのヴォーカルはしっかりとしており、安定感がある。キーボードの使用量が少ないためにこの時代特有の影響をあまり受けていないように聴こえる。そのため、多少は普遍性のある音に仕上がっているようにも思える。プロデュースはReeves GabrelsとTom Dubeによる。最後に隠しトラックの"Fly in the Nursery"が収められている。"Sam"の最後の部分に挿入されている曲は誰かの曲だと思うんだけど…思い出せません。 |
 |
Protecto "Sonicnauts" ('06) |
Reeves Gabrels(g、fretless b、loops)がStefan "Big Swede" Svensson(ds、keys、percussion、loops、samples)と組んだテクノ/ハウス系ユニット。オープニングの"Prtotecto Calling"こそキーボードやループ系の音に支配された、よくある音に聴こえるのだが、やはり、そこはReeves Gabrels。続く"I'm Always Ready to Entertain You"からノイジーで、時にスペーシーなギターサウンドを叩き込む。タイトルから容易に音が想像出来る"Anything Curry"には、シタールっぽい音も聴こえる(なんだかなぁ)。また"Coyote"のギターソロの情感は流石。"Nightbluc in Texas"もタイトル通りの予想を裏切らない音が出てくる。バンジョーっぽい音や、ジャジーなギター。ブルージーな曲。全体的に意外と楽しめる盤になっている。 |
Sessions
 |
Sean Malone "Cortlandt" ('96) | 元CynicのSean Maloneのソロ・アルバム。John Coltraneの"Giant Steps"のカヴァーを含むテクニカルなジャズ・ロックを展開する。ドラムにCynic時代の相方Sean Reinertを迎え、よりジャズ寄りな曲ではセッション・ジャズ・ギタリストBob Buninを起用、テクニカルでメタリックな"Splinter"では(Geoff)Caputoを起用。その他、"At Taliesin"ではReeves Gabrelsがギター・ソロで参加。"Big Sky Wanting"ではTrey GunnがWarr Guitarとタッチ・ギターの共演となっている。最後の"Big Idea"ではヴォーカル・コーラスが挿入されているが、ここにJohn Wesleyの名前も。プロデュースはScott Burns、と、基本フロリダ人脈。ジャズ曲でさえも、Sean Maloneのプログラミングやループなどが入っているので、サウンドは非常にモダンで独創性に溢れていると言える。テクニカル・メタルに興味があれば、是非聴いておきたい作品。因みに本編終了後30分以上経ってからボーナス曲のバッハのシンフォニア4番が出てくる。 |