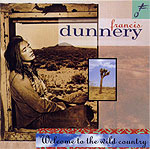

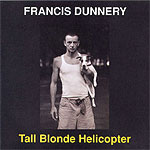



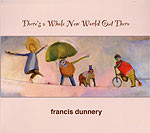

Francis Dunnery
90年にIt Bitesを離脱してから、この人のキャリアは面白くなる一方。再結成It Bitesの話が出ていたけど、参加せずに正解だと(個人的にはね)。NYCで一人で楽しくアコギを持ってステージ上で体を揺すりながら歌う姿は、何処か達観したところがあって。これがFrancis Dunneryの伝えたいことかぁ、と。
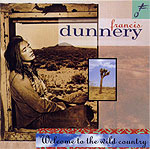 | Welcome to the Wild Country ('91) | It Bitesを脱退してからの最初のソロアルバムは、ソロ名義でありながらも、バンド形態での録音となった。クレジットされているのはNan Bador(ds)、Vegas Lea(b)にGenesisなどのプロデューサーとして名を馳せたDavid Hentschel(piano)。David Hentschelは今作のプロデューサーも担当。It Bites時代とは全く違う音で勝負したいのは、タフで埃っぽい大陸的なハードロックな音からも容易に想像が出来たが、まさか、ここまでの変化を必要としていたとは正直驚きではあった。女性ボーカルを従え、ビックコーラスを取り入れる。時にギターの音はエレクトリックヴァイオリンのような音を出すのは、カントリー等からの影響?ガッツィーな表題曲、近年でもライブで披露されることが多いらしい"Jackal in Your Mind"(つまり、アコースティックセット中心の彼のライブで歌いやすいってことなんでしょう)、ゴスペルコーラスが気持ち良い"Just like My Father Said It would Be!"(父親を直前に失くされていて、このアルバムは父親に捧げられている)、そして壮大な"The Possibilities of Loving You"と多彩な楽曲が目白押し。契約上の問題からか、当初は日本のみの発売だった。01年に"The Mother & Father of Love"と"Peace for Our Time"を足して再発された。 |
 | Fearless ('94) | ソロ・アーティストとしてマルチプレイヤーぶりを発揮しはじめた2nd。大手Atlanticよりの発売となった。Francis Dunneryはvo、g、ds、b、programmingを担当。プロデュースを担当したKevin Nixon(b、harmonica)、Matt Pegg(b)、Mark Parnell(ds)、このアルバム以降、大ブレイクしセッションマンとして引っ張りだことなるDave McCracken(programming)が参加。非常に英国人らしい捻くれたセンスの歌詞にポップでキャッチーでありながら、どこか屈折した曲が並ぶ。一聴して、前作と違い、ハードさは影を潜めポップになった印象は確かにある。ストリング、ホーンや女性ボーカルを配し、多彩なアレンジを施した楽曲が並ぶ。そういった楽曲に共通しているのが、どこまでもブルージーに鳴るギターと声。"Feel like Kissing You Again"の大仰な曲でもブルーズフィーリングをきっちりと出し、そこから雪崩れ込む"King of the Blues"では、抑制の効かない感情の発露を見事に描き出す。ある意味、コントロールが効いていないアルバムなのかもしれない。だからこそ、それを素直に出す姿に共感が持てる。こういう曲でもブルージーなギターは掻き鳴らせる。それが根底にあるから、多彩な楽曲に大仰なストリングやホーンのようなアレンジを施しても筋が通っているのだろう。だから"Fearless"…。納得。 |
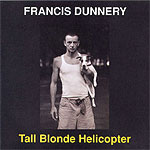 | Tall Blonde Helicopter ('95) | ある意味、前2作の作風を合体させたかのような3rd。1stのロウな生々しさを残しつつ2ndで見せたキャッチーなセンスを上手く融合させていると言えるだろう。プロデューサーはClannad等で名を馳せたRichard Dodd。今作に関わっているのは、実はいずれも一癖も二癖もありそうなタイプでそれぞれがソロキャリアを持っている。Pat Buchanan(g)、Greg Morrow(ds)と言ったところから、何とThe E Street BandからBrad Jones(b)まで呼んでいる。更に"Rain or Shine"ではJill Sobule(vo)との共演を含む。Cat Stevensの"Father and Son"(Tea for the Tillermanより)のカバーも、今作にぴったりと合っている。サウンドの装飾も必要以上に施さず、かと言って、決して無味乾燥な音には絶対に仕上げず。そのバランス感覚は良い。歌詞も徐々に等身大の自身を見つめる作風は説得力を増し、力強さを感じさせる。ある意味シンガーソングライター・タイプの作風ではあるけど、決して退屈な音を出していない。 |
 | Let's Go Do What Happens ('98) | 前作で見せた内省的なシンガーソングライターのような作風に捻りを加えた方向性を自身の音楽性を見出したFrancis Dunnery。基本的に今作も前作と同じ路線を踏襲する。こういった作風の場合、どのプロデューサーやミュージシャンと組むかで音の出方が変わってくる。全12曲中5曲でStephen Harrisとの共同プロデュースで残りはFrancis Dunnery単独プロデュースとなっている。まずは何と言ってもCaptain Beefheart等で活躍したGary Lucas(g)の参加であろう。随所でツボを得たプレイを聞かせる。その他にGraham Hawthorn(ds)、Doug Petty(key)、Jon Montagna(b)、Joe McGinty(key)等が参加。スペーシーなキーボードをバックにした"My Own Reality"やネット接続時のダイアルアップの効果音が印象的なハードな佳曲"Crazy is a Pitstop"などサウンドに工夫が凝らされているのも特徴だろう。アルバム全体を通して、時折聞こえるメロトロンの音も効果的。作風が似ているが故、だろう。 |
 | Man ('03) | 前作では一部のみ単独プロデュースを行ったFrancis Dunneryだが、今作で初めて1枚丸まるセルフ・プロデュースで作品を制作。名盤"Fearless"で組んだDave McCracken(prog、synth)とMatt Pegg(b)を中心に迎え、バックヴォーカルを充実させチェロプレイヤーを2名用意し、曲に彩りを添える。基本路線は従来通りのシンガーソングライター・タイプのシンプルな曲に、そこかしこにセンスの良いアレンジが施されている。こういったアレンジこそFrancis Dunneryの真骨頂であり、既にトレードマークと言えるだろう。歌(詞)を中心に置きつつも、決して安易なアレンジで済ませない所は流石。前作よりはハードさは後退したが、それも意味はない。シンプルな故の名盤。 |
 | The Gulley Flats Boys ('05) | 驚いたことに、2枚組のアルバムを出してきたFrancis Dunnery。過去5年間、所謂ミッド・ライフ・クライシスのようなものを経験して、非常に後ろ向きだったのが、やっと前向きになれた、という旨のライナーがあり、それが、ある意味このアルバムに結実した結果となった模様。曰く、その時の日記のようなものだった、という。その為には、もしかしたら、全てを吐き出す必要があり、それが2枚組という事になったのかもしれない。表題の"The Gulley Flats Boys"は幼少期Francis Dunneryがつるんでいた悪ガキ共の愛称。音の方は、名手David Sancious(key他)を迎え、ヴォーカル、ギター、鍵盤というシンプルで、丁寧に言葉を印象的に紡いでいく。ノスタルジックな場面もあれば、優しさを感じることもある。繊細、というよりは、丁寧、という言葉が似合う感じがする。そして、近年のFrancis Dunneryの姿そのまま、でもあると思える。殆ど、ステージでは一人ギターを抱え、メロディーに自分の言葉を乗せる姿がそのまま、このCDにはパッケージングされている。Francis Dunneryのワンマン・ライブを思い出す。 |
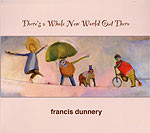 | There's a Whole New World Out There ('09) | It Bitesの再録を中心とした2枚組。Francis Dunnery自身、新しいプログ・ロック・アルバムを作るとアナウンスしたものだから、勘違いしてしまった人も多い、ちょっと迷惑なアルバム。更に困ったことにEcholynからPaul Ramsey(ds)、Brett Kull(g)、SpiralingのTom Brislin(p、synth)、そしてJamie Bishop(b)とDorie Jackson(vo)というそれっぽい編成にしてしまったから尚更である。Francis Dunneryが追求する声と言葉に極力ストリップ・ダウンさせたサウンドは近年のFrancis Dunneryの姿そのものを正直に伝えている。そういう意味ではFrancis Dunneryの言うプログ・ロック・アルバムという表現も正しくIt Bitesと同じ装飾をしてしまったら何ら進化のないものになってしまう。時にスウィートでジャジーに掻き鳴らされるギター、品の良いピアノにDorie Jacksonの声が曲に新しいアクセントを付ける。It Bitesの再録以外にもRobert Plantの名曲"Calling to You"、Genesisの"Back in New York City"、Joy Divisionの"Love will Tear Us Apart"(現It BitesのJohn Mitchell参加)、Japanの"Still Life in Mobile Homes"(Theo Travis参加)といったカヴァーの選曲も秀逸。 |
 | Made in Space ('11) | 本作はFrancis DunneryがAuto Tuneと呼ばれるソフトウェアを使用してヴォーカルを録った作品。そのため、全編ヴォコーダーのようなエフェクトがかかったヴォーカルが聴ける。本作にはお馴染みのDorie Jacksonを迎えた他、ラップ・ヴォーカルにAva D.(多分Francis Dunneryのお嬢さんのAva Dunneryでしょう)とクレジットされている人物のみが参加。プログラムを全てFrancis Dunneryが手掛けている。コンテンポラリーなソウル、R&Bに影響されたバックビート、サウンド・レイヤーの上にFrancis Dunneryの叙情的な声が載る、というもの。本作は生まれたばかりのElisie Dunneryに捧げられており、そういう意味でも非常にパーソナルな仕上がりとなっている。 |
It Bites
 | The Big Lad in the Windmill ('86) | Produced by Alan Shacklockの文字を見て、ちょっと喜んだことを正直に告白しておこう。このBabe Ruthの音楽性を担っていた男は、80年代に入ってからプロデューサーとして、The Alarmの1st、Roger Daltreyの"Under the Rising Moon"とプロデュースを手掛けてきた。このラインナップを見れば、自ずとその音楽性が見えてくるだろう。"Whole New World"のホーンセクション等はその良い例だろう。"Wanna Shout"などのニューロマンティック的な肌理の細かいサウンド・アプローチ、全編に渡って聴かせるアンセム的な盛り上がりを持つヴォーカル・ハーモニー。"Screaming on the Beaches"あたりで聴かせるJohn Beckのプログレっぽいサウンドも幅の広さを証明する一要因にしか過ぎない。ジャケットも何とも英国的な印象を持たせる。裸足の右足を上げて、イーゼルに向かう男の描く絵は風景と似た色彩を持つものの絵そのものは全く違う、というもの。作曲は全てバンド名義による全10曲。下積み時代の成果が発揮された良作。 |
 | Once around the World ('88) | アルバム前半がSteve Hillageプロデュース(レーベル関係?)で後半はバンド名義のプロデュースとなっている2nd。流石にサウンドのダイナミズムが向上しているように聴こえる。意外とテクニカルなギターを弾きたがるFrancis Dunneryに、サウンドの要となるJohn Beckのキーボードという軸は変わらず。ダイナミズムが上がった分だけスケールが大きくなった。勢いのあるキャッチーな曲をSteve Hillageが担当して、"Old Man and the Angel"や"Once around the World"のような、ある意味オールドウェイブとも取られそうな大作がバンド・プロデュースというのも何となく判る。このあたりの中間部が持つアイディアは確かにプログレ的。更に(後半の)歌詞が非常にGenesis、というか、Peter Gabriel的な言葉選びのセンスに英国魂を感じる。やはり、最後の表題曲の持つ世界観に心が揺さぶられてしまうのは性か?全曲、バンド名義による作曲。 |
 | Eat Me in St.Louis ('89) | Mackのプロデュースによる3rd。Mack=Queen=ヴォーカル・ハーモニーという図式は誰でも思い起こすところ。オープニングから、その期待を裏切らないヴォーカル・ハーモニーから入るところは何を期待されているのか、何を充実させたかったのか、一聴瞭然、と言ったところか(私が持っている日本盤は"Sister Sarah"から始まる)。更にIt Bitesカタログの中で最も緻密なアレンジとプロダクションを誇る作品となった。特筆すべきはFrancis Dunneryのヴォーカル・プレゼンテーションに更に磨きがかかった点だろうか。楽曲の表情をより豊かにするために多彩なヴォーカルを披露する工夫が見れる。時にストレートで、ハードでありながらも、英国らしいシアトリカルなパートも聴ける。"Underneath Your Pillow"あたりは良いサンプルかもしれない。"Let Us All Go"が持つグルーヴ感もQueenが持っていたグルーヴに近い感じを受ける。また日本盤には"Vampires"が8曲目に収録されており、全12曲。"Sister Sarah"と"Positively Animal"とが入れ替わっていた。アルバム最後を飾る"Charlie"はFrancis Dunnery作のギター・インスト。肌理の細かいアコースティックギターが印象的な繊細な曲。ジャケットはRoger Dean御大。 |
The Syn
 | The Syn "Big Sky" ('09) | 60年代にシングルを発表したYesの前身グループの一つをSteve Nardelli(vo、Nardellitron)が05年に旧曲と新録を合わせたアルバムで復活。更にSteve Nardelliはここで伝説のグループというレッテルを剥し、09年に相応しいリアルなグループとして再びバンドを纏め上げたのが本作。まずFrancis Dunnery(g、b、key、vo)をパートナーに全曲共作し、プロデュースも任せている。キーボードにYesのSymphonic Tourに参加したSpiralingのTom Brislin(key)を起用。更にEcholynのPaul Ramsey(ds)を迎える。CDにはクレジットはないが(オフィシャル・サイトにはクレジットがある)同じくEcholynからBrett Kull(g)が参加しているよう。ミキシングも担当。ある意味、このメンツのポップ・サイドが爆発した名盤。掠れ気味のヴォーカルを披露するSteve Nardelliは時に高音になるとJon Andersonを思わせるパートが幾つか出てくる。効果的なアコースティック・ギターの使い方やバック・ヴォーカルの入れ方(や女性ヴォーカルの使い方)が非常に「らしい」Francis Dunnery。多彩なサウンドで楽曲を邪魔せずに彩りを加えていくTom Brislinの働きが非常に良い。時にYes風であったり、クラシカルなパートはProcol Harumあたりをサウンドを思い出させる。これは正に名盤としか表現のしようがない。 |
Other involvements
 | Robert Plant "Fate of Nations" ('93) | Page Plant前夜、Robert Plantソロ6作目。"Now & Zen"あたりから、ふっきれた感のあったRobert Plant。"Network News"などに見られるように社会性の強いテーマを持っているようだ。その反面、"I Believe"のような非常にパーソナルな曲もある(Eric Claptonの"Tears in Heaven"と同じ位置付け)。リラックスした雰囲気の中、あちこちで非西洋圏の音が聴こえるのも特徴だろう。Nigel Eatonのハーディーガーディーやサロード、サランギ、ウドゥらしきパーカッションの音もあちこちに配しているようだ。ギター陣はKevin Scott MacMichaelを筆頭にDoug Boyle(後にCaravanのメンバーとして来日する)を中心にFrancis Dunneryも"Come into My Life"(Richard Thompsonも参加)と"Promised Land"に参加。Tim Hardinの"If I were a Carpenter"のカバーも、アルバム全体に馴染んでいる。またPink Floyd的な残り香を漂わせる"The Greatest Gift"やLed Zeppelin的な世界観を持つ"Memory Song(Hello Hello)"と秀作揃い。Robert Plantだけが為しえることが出来た名盤中の名盤。ジャケットが変色しているのは気にしないで下さい。理由は忘れたけど、確か洗剤をこぼした…。何で、やったんだろう??? |
 | Ian Brown "Music of the Spheres" ('01) | 元The Stone RosesのヴォーカリストIan Brownの3枚目のソロ作。プロデューサーにDave McCracken(key、programming)を迎えている。ドラムレスのため、Dave McCrackenのプログラミングがビートを刻み、リラックスしたIan Brownのヴォーカルのともすればナイーヴに聴こえる声をサポートし、音世界を作り上げている。Francis Dunneryは全曲でギターで参加。スペイン語で歌われる"El Mundo Pequeño"では繊細なアコースティック・ギターをかき鳴らし、続く"Forever and a Day"のイントロではブルージーでハードなギターを披露する(この2曲では共作者としてもクレジットされている)。オープニングの"F.E.A.R"は"For Each A Road"、"For Everyman A Religion"と単語の頭文字が全て"FEAR"になるように言葉を繋いだクレヴァーな歌詞が特徴。Francis Dunneryのギターは力強くハードな音像が多いがDave McCrackenのプログラミングが上手くサウンドを被せ、Ian Brownの歌とマッチするように調度良いバランスを保っている。"Hear No See No"はMark "Dog" SayfritzとDave McCrackenによるうねる様なサウンドスケープにIan Brownの声がコラージュされたようなミニマリスティックな作品。オープニングの"F.E.A.R"と最後の"Shadow of a Saint"にストリングスがふんだんに使われている。 |
 | Stephen Harris "Songs from the Mission of Hope" ('03) | シンガー・ソング・ライターStephen Harris(g、vo、dulcimer、harmonica)がFrancis Dunnery(g、p、mellotron、perc.)とチームを組みしっとりと聴かせるFrancis Dunneryが得意とするタイプの作品。Matt Pegg(b)が2曲で参加。更にLousia Mitchellがヴァイオリン、Shaula Lumleyがフルートで参加し、単調になりそうなサウンドに絶妙な色彩を加えている。Stephen Harrisは長い間うつ状態が長く、掛かりつけのドクターから生みの母親を探すことを勧められ、ついに彼女との再会を果たす。タイトルとなっているThe Mission of HopeはStephen Harrisの生母が育った孤児院で育ったことを知り、その孤児院の名前がThe Mission of Hope。このアルバムはそんなStephen Harrisの私小説的な曲の数々だろう。シンプルな構成、サウンドにも関わらずモノトーンにならずカラフルな曲の数々はそんなStephen Harrisの優しさを示唆しているよう。美しい作品である。因みにStephen Harrisは以前はKid ChaosとしてZodiac Mindwarp and the Love Reactionに在籍していた。 |
 | Dorie Jackson "The Courting Ground" ('07) | Francis Dunneryと一緒に活動を共にしているDorie Jacksonのデビュー・アルバム。プロデュース、共作、ギター、キーボードでFrancis Dunneryが携わる。その他に元Level 42のNathan King(b)、Trevor Smith(ds)、Melvin Duffy(pedal steel、dobro)、Flamman(g)、Terry Smith(mandoln)、父親である元Van Der Graaf GeneratorのDavid Jackson(sax、flute)が参加。冒頭の"Songbird"は深い声を使ってアラビック風なアレンジなど広がりのある世界観で始まる。"Railway Station Boy"は元Zodiac Mindwarp and the Love ReactionやThe CultにいたKid ChaosことStephen Harrisによるナンバー。 続く"Back Again、Starry Eyed"もStephen Harris、Dorie Jackson、Francis Dunneryとの共作。それ以外の楽曲は全てFrancis Dunneryとの共作となる。冒頭曲以外はシンガーソングライター・タイプらしい優しい感じの曲調が多い。コーラスの入れ方やちょっとしたギター・フレーズにFrancis Dunnery特有のサウンドがしっかりと刻印されている。特に"The Deep Sea Life"などはFrancis Dunneryのソロに入っていてもおかしくないような曲。"Too Scared to Say I Love You"はちょっとカントリー・タッチが入る曲。表題曲でである愛らしいヴォーカルとアレンジが美しい"The Courting Ground"で締め括られている。 |
 | James Sonefeld and the Christmas Brass "Snowman Melting ('08) | Hootie & the BlowfishのドラマーJim "Soni" Sonefeld(vo)のソロ・アルバム。元Level 42のリズム隊Nathan King(b)、Trevor Richard Smith(ds)とFrancis Dunnery(g、key)にThe Christmas Brass BandのBilly Christmas(sax)、Barry Christmas(french horn)、Terry Christmas(trumpet)というバンド形態による。Francis Dunneryプロデュースで、Francis DunneryのレーベルAquarian Nationからリリースされている。Aquarian NationによくあるFrancis Dunnery印があちこちに刻み込まれている作品。表現者として強いものがないと、このFrancis Dunneryプロデュースには飲み込まれてしまう、という悪い例にしか聴こえない。Francis Dunneryが何から何まで手取り足取りで作った、という印象。Francis Dunneryのプロデュースーとしての資質や限界も露呈してしまっているかもしれない。Francis Dunneryのアレンジなどを楽しみたい人向け。 |
 | Big Big Train "The Underfall Yard" ('09) | ドラマーにSpock's BeardのNick D'Virgilioを迎えて格段にパワーアップしたBig Big Trainの6枚目。ヴォーカルにMartin Orfordのソロなどにも参加したDavid Longdonが参加。このDavid Longdonがフルート、マンドリン、ダルシマー、オルガンとサウンドに様々なカラーを添えるのに一役買っている。その声はPhil Collins脱退後のGenesisのオーディションに呼ばれるだけある声をしている。Andy Poole(b、key)、Greg Spawton(g、key)のプレイは時にYesなどを強く意識させる。流れるようなジャジーなプレイをふんだんに聴かせるNick D'Virgilioのプレイが聴き手をグイグイと引っ張る様が圧巻。殆どの曲でギターソロはDave Gregory(元XTC)によって演奏されている。Francis Dunneryは表題曲でギター(とギターソロ)で参加。その他にもFrostのJem Godfreyなどが参加してる。またアートワークや歌詞をみると英国の鉄道や鉱山で働く人たちの様子を描いているようで、こちらも非常に興味深い。名作。 |