
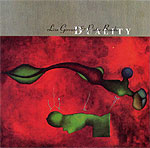
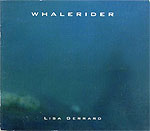
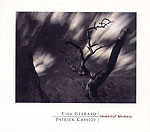




Lisa Gerrard
 | "The Mirror Pool" ('95) | オーストラリアのVictorian Philharmonic Orchestraをふんだんに使い、深いコントラルトのヴォーカルが深遠な世界へと導くように響く。オーケストラ以外にDimitry Kyryakouがブズーキなどで参加。同郷のパーカッショニストPieter Bourke、キーボード奏者のJohn Bonnarなどが参加している。"Persian Love Song (The Silver Gun)"はイラン南部の伝統曲、"Largo"はヘンデルのオペラ「セルセ」から。正式タイトルは"Ombra mai fu"と呼ばれる。呪術的なチャント、詠唱が占める"The Rite"から"Ajhon"への繋がりが表すプリミティブな世界がある一方でLisa Gerrardが得意とする楊琴(ハンマーダルシマーのご先祖らしい)の優雅なサウンドや"Largo"の世界観と、その振幅は非常に広い。"La Bas (Song of the Drowned)"は青ひげことジル・ド・レー元帥を扱ったフランス作家ユイスマンスの「彼方」をモチーフにしたもの。後にサントラを手掛けるLisa Gerrardの原点がこのあたりかもしれない、非常に映像的な曲。"Celon"はトールキンの「指輪物語」に出てくる川の名前。"Majhnavea's Musical Box"と"Werd"はインスト曲。 |
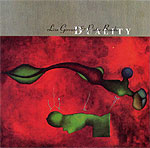 | Lisa Gerrard & Pieter Bourke "Duality" ('98) | Lisa GerrardがDead Can Dance解散後初めて世に出した作品。ここに収められている全てのパフォーマンスはLisa GerrardとPieter Bourkeによるもの。パーカッション類はトライバルで己の根源を探るかのように聴き手を揺さぶるリズムを持つ。メロディーは時に中東やアジア圏からの引用やヨーロッパらしいものが混在している。"Tempest"と"Sacrifice"はアル・パチーノ主演映画「The Insider」に使用された。深く響くLisa Gerrardのコントラアルトを軸に音世界が広がっていく情景はどんな楽器よりも饒舌かもしれない。それ故、使用楽器もエレクトロニックよりも古楽器などが中心になるのかもしれない。"The Unfold"の世界観はLisa Gerrardのみ表現出来るものだろう。"The Human Game"ではLisa Gerrardが得意とする楊琴の音色が聴こえる。 |
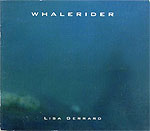 | "Whalerider" ('03) | 邦題「クジラの島の少女」という映画のサントラ盤。ニュージーランド、マオリ族の伝説をモチーフにした映画に相応しい透き通るようなサウンド・スケープが聴ける。暗がりの海の中にぽつりと浮かんでいるような情景が浮かぶ"Paikea Legend"や楊琴のポジティブな音が鳴る"Biking Home"、Phil Pomeroyのピアノを擁した"Pai Theme"などがある。また、この映画の舞台となるニュージーランドのワンガラ族のNgati Konohiの人たちによるハカ(マオリ族の民族舞踊;ニュージーランドのラグビーチーム「オールブラックス」がやっている儀式)の音がアルバム最後の"Waka in the Sky"と"Go Forward"に収められている。 |
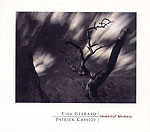 | Lisa Gerrard / Patrick Cassidy "Immortal Memory" ('04) | アイルランド出身の作曲家Patrick Cassidyとのコラボレーション作。Patrick Cassidyの亡くなった父親に捧げられた"Psallit In Aure Dei"を除いて全て共作となっている。ストリングスを中心としたオーケストレーションが静謐な叙情性を醸し出し、Lisa Gerrardの力強くも憂いのある全てを包み込むような美しい声が被さる。冒頭の"The Song of Amergin"ではゲール語で歌い、"Maranatha (Come Lord)"と"Abwoon (Our Father)"ではアラム語(キリストの時代に話されていたセム族の言葉)、"Psallit In Aure Dei"ではラテン語の歌詞を歌っている。その他の曲ではLisa Gerrardらしいスキャットやチャントが魂の深くを呼び起こすようなコントラルトで曲の風景を象っていく。最後のPatrick Cassidy作の"Psallit In Aure Dei"はLisa Gerrardにとって初めて他人の歌詞を歌う作品となった。「映画のないサウンドトラック」と呼ばれたように壮大な音楽が繰り広げられいてる名作。 |
 | "The Silver Tree" ('06) | ジャケットが映し出すような「深遠」という言葉をサウンドにしたら、こんな音になるのではないだろうか、という印象を持たせる。祈りとも嘆きとも聴こえるような深い詠唱のようなヴォーカルから始まる"In Exile"と10分にも及ぶ動のリズムと静のヴォーカルという組み合わせを持つ"Towards the Tower"のオーケストレーションにPatrick Cassidyが参加。それ以外のパフォーマンスは全てLisa Gerrardによる。後半のスキャットが何となく「2001年宇宙の旅」を思わせる"Space Weaver"のみMichael Edwardsとの共作。コントラアルトという深い声を主に使うLisa Gerrardにしては、この曲は女性らしい、ちょっとコケティッシュにさせ聴こえる声で表現しているのが非常に珍しい。静謐さの中に音の広がりにこだわりを持った作品、という印象を受ける。心に響く、というよりは脳の奥底に眠る人間の太古の記憶に訴えるかのようなサウンド。最後にDead Can Dance的な隠しトラックあり。 |
 | Klaus Schulze Lisa Gerrard "Farscape" ('08) | タイトル通りKlaus Schulzeの音楽にLisa Gerrardの声が乗る、というもの。ライナーノートを読むと、非常に密度の濃い創作時間だったようだ。Lisa Gerrardのヴォーカルは全て即興で録音されている。電子音楽、シンセサイザー音楽として知られるKlaus Schulzeのその音楽性はある種有機的に聴こえるのは、Lisa Gerrardの声との融合のせいだろうか。Lisa Gerrardの声がKlaus Schulzeの持つサウンドの波形を際立たせ、絡むように昇華させている。Klaus Schulzeのサウンドはスペーシーであったりビートが利いたものだったり、と多彩な表情を持ち、Lisa Gerrardも深いヴォーカルやチャント風のもの、幼子のような声などを用いて、Klaus Schulzeのサウンドの世界観を彩っていく。"Liquid Coincidence"と呼ばれる曲が7曲、約2時間半の芳醇な音楽が2枚組で用意されている。 |
 | Lisa Gerrard with Klaus Schulze "Come Quietly" ('09) | Lisa Gerrardの英詩の朗読に独特な謳い回し、詠唱をKlaus Schulzeの前作よりはメロディーが前面に出たサウンドが包み込むように配されている25分程度7曲入りのミニ・アルバム。Klaus Schulzeと組んでも変わらない静謐さを醸しだすLisa Gerrardの世界観の強さがサウンド・イメージを決定付け、聴く者を圧倒する。リズミカルな展開を最後の最後に持ってくる"Surrender to Silence"はKlaus Schulzeの世界観を強く感じさせる。Lisa GerrardとKlaus Schulzeが作り出した"Farscape"とは全く違う側面を見せてくる。 |
 | Black Opal ('09) | 前半は深遠なLisa Gerrard特有のアンビエンスと深い声に包まれるような楽曲が並ぶ。Lisa Gerrardが得意とする映画のサウンドトラックのようにサウンドに映像が浮かぶような表情豊かな楽曲で構成されている。後半アコースティック・ギターをサウンドの主軸に置きながらも、静謐な世界観を醸しだす"The Serpent & the Dove"以降が興味深い。Bob Dylanの"All along the Watchtower"のカヴァーは打ち込みサウンドを加えながらBob Dylan風のヴォーカルを披露する。ある意味、俗っぽくもあり、親しみやすい楽曲が並んでいる。最後の"Sleep"などはSinéad O'Connorをも思い起こさせる。言わば、Lisa Gerrard流ポップ・シンガーを見せてくれた作品。意外と入門篇としては良いアルバムかもしれない。デラックス・エディションではボーナス・トラックや映像が入った2枚組となっている。本作ではMichael MannとPieter Bourkeが協力している。 |
Dead Can Dance
ニュージーランド出身のThe Marching GirlsというバンドにいたBrendan Perry(g、vo)とSimon Monroe(ds)がPaul Erikson(b)と合流。最後にLisa Gerrard(vo)を迎えて81年に結成。翌82年、バンドはSimon Monroeを除いてロンドンに拠点を置くが、Paul Eriksonはバンドを離れ、オーストラリアへと戻り、Brendan PerryとLisa GerrardのデュオでDead Can Danceとして4ADと契約する。
 | Dead Can Dance ('84) | ドラマーにPeter Ulrichを迎えて製作された1stアルバム。基本的にデジタルなビートにエスニックなパーカッションなどを加えたサウンドが聴こえる。一般的にレーベルカラーをよく表したポジティブパンクとかゴシック・ロック等と呼ばれるサウンド。オープニングの"The Fatal Impact"(インスト)からも一風変わったサウンドを持ったグループというのが窺える。"Frontier"、"Ocean"、"Threashold"、"Musica Eternal"でLisa Gerrardの歌声が聴こえる。女性ロック・ヴォーカルにしてはコントラルト(テナーとメゾソプラノの間)を多用し、深いヴォーカル・パフォーマンスを演出している。その他ではBrendan Perryがヴォーカルを取る。ロック色が強い曲では確かにThe Missionあたりを思い起こさせたりもする。CD化の際に同年に出されたEP"Garden of the Arcane Delights"に収録されていた"Carnival of Light"、"In Power We Entrust the Love Advocated"、"Flowers of the Sea"が足される。このEPでもPeter Ulrichがドラム、パーカッションを担当。ジャケットに描かれているのはニューギニアの先住民族が儀式に使うマスク。生きている木から切り落とされ命を失った材木が人の手によって、マスクとしてその生命を再び吹き込まれ、儀式に使われる、という生から死、死から生というサイクルを表しており、その象徴がこのマスクでありDead Can Danceの音楽の目指すところ、ということなのだそう。 |
 | Spleen and Ideal ('85) | Brendan PerryとLisa Gerrard以外はチェロ、ティンパニー、トロンボーン、ヴァイオリン等のプレイヤーが参加。それ以外の音とヴォーカルは全てBrendan PerryとLisa Gerrardで作り上げられた。オープニングのグレゴリアン・チャントから始まる所からして、既にロックミュージックからの逸脱が聴き取れ、更に幅広い音楽性、特に中世音楽や教会音楽への憧憬を感じる。欧州のみならず、中東等からの影響も聴こえる。これはBrendan PerryとLisa Gerrardの二人のメンバーのみが残った結果かる来る方向性ではなく、やはりDead Can Danceが体現したかった音世界なのだろう。"Mesmerism"のタイトル通りの幽玄さ、耽美な世界に代表されるようなナンバーに息を呑む。アルバム・タイトルはCharles Pierre Baudelaireの"Les Fleurs du mal"(邦題「悪の華」)の冒頭の章から取られているのは興味深い。またその他にもThomas de Quinceyの"Confessions of an English Opium-Eater"(邦題「阿片常用者の告白」後にCharles Pierre Baudelaireにも訳される)からの引用もあるようだ。 |
 | Within the Realm of a Dying Sun ('87) | 前作と同様にヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、トランペット、トロンボーン、チューバ、オーボエ奏者にPeter Ulrichがティンパニーとミリタリースネアで参加。それ以外の全てはBrendan PerryとLisa Gerrardがヴォーカルとインストルメンツを担当という形。オープニングのBrendan Perryと深い声に深遠なシンセがバックに流れる。"Xavier"でLisa Gerrardのスキャットに導かれるように始まる。前半はBrendan Perryのヴォーカルで、後半からLisa Gerrardのヴォーカルと分けてある。そのLisa Gerrardのヴォーカルは今作から劇的な変化が見られる。後半に入り、"Dawn of the Iconoclast"でアラビア語ともラテン語ともつかない言語で歌っているようだが、どちらも違っている。今作では彼女のヴォーカルは全てグロッソラリア(異言)で占められている。正に「Iconoclast」(因習打破)に相応しいかもしれない。"Cantara"でもBrendan PerryがLisa Gerrardに合わせるように声を重ねていく。このヴォーカル技法によって、Dead Can Danceの音楽がよりパワフルでプリミティブな世界を描いている。ヴォーカルを意味から解き放ち、純粋にメロディーとして成立させる。それでも決して単調な音の連なりを嫌い、多様な音をあたかも意味があるように歌うその様は確かに宗教的でさえある。 |
 | The Serpent's Egg ('88) | Lisa GerrardとBrendan Perryはヴォーカルにほぼ専念(Brendan PerryはHurdy-Gurdyのみ演奏)。それ以外はクレジット上はストリングスを配したのみとなっているが、多少のキーボード等は入っているよう(それでも、最小限に留めている、という印象)。この過程はある意味、当然なステップだろう。よりオーガニックな人の声と弦とのアンサンブル。特にLisa Gerrardの使うグロッソラリアやスキャットとのマッチングは古の教会にでも誘うかのような静謐さを持っている。対してBrendan Perryの声は深く、違ったアクセントを持つ。こちらは英語詞がメイン。"In the Kingdom of the Blind The One-Eyed are Kings"の叙情的に始まるオープニングから後半のビックなオーケストレーションを置いた大仰さは聴き手をドキドキさせるだけのスケールを持つ。Lisa Gerrardの勇壮なヴォーカルとレクイエム的なサウンドの相反する組合せが印象的な"Chant of the Paladin"、呪術的なムードを漂わすBrendan Perryの声を復唱するLisa Gerrardの"Echolalia"からトライバルでパーカッシヴな"Mohter Tongue"への移行など、徐々に移行する様子が印象的。オープニング・トラックの"The Host of Seraphim"は映画「バラカ」でも使用された。 |
 | Aion ('90) | 基本的にLisa GerrardとBrendan Perryがインストルメンツとヴォーカルを担当。その他にJohn Bonnar(Roger Eno等とのコラボレーション有り)がBrendan Perryが歌うシンフォニックでさえある、美しい名曲"Fortune Presents Gifts Not According to the Book"(歌詞はスペインの詩人ルイス・デ・ゴンコラが1581年に発表した「Letrillas」から)でキーボードを担当。今作の特徴として"Saltarello"のような14世紀のイタリアのダンス曲や同系統の"As the Bell Rings the Maypole Spins"といったバグパイプ入りのステップを踏みたくなる曲や中東風の舞踊曲を思わせる"Radharc"がある事。ある種、通俗的とでも言えようか。一方で預言者が黙示録を語る様を歌う"The Song of the Sibyl"やグレゴリアン・チャント風の"The End of Words"といった今までの路線を踏襲する曲もある。更に"Black Sun"ではECM的でもある切迫感のあるバックに朗々とBrendan Perryが歌う様は今までにない世界観のように感じる。"The Promised Womb"ではテナー・ヴィオールとバス・ヴィオールを2本ずつ計4本をバックにLisa Gearrardの力強いコントラルトが聴ける。ジャケットはヒエロニムス・ボスの「快楽の園」の中央の地上絵の更に中央部から。名作。 |
 | A Passage in Time ('91) | アメリカで発売されたDead Can Dance初のベスト。98年にワールド・ワイドで発売された。音楽性の差異からだろう、当然ながら1stからは選曲されていない。"Spleen and Ideal"から1曲、"Within the Realm of a Dying Sun"から2曲、"The Serpent's Egg"から6曲、"Aion"から5曲に未発表曲が2曲という構成。未発表の"Bird"はまるでジャングルに迷い込んだかのような鳥のさえずりがメインのS.E.がまるでメロディーのよう鳴る中、パーカッションが響き渡る。Lisa Gerrardの呪術的な声が遠くに聴こえる。続く"Spirit"はジャジーな感じさえもするベース音にBrendan Perryのニューウェーブ・バンドにありがちな感じの広がりのあるヴォーカルを聴かせる。曲調としては1stに通じるものがあるものの、その生々しさを備え持ったエレクトロニクスな感じは1stでは出せなかったサウンド。 |
 | Into the Labyrinth ('93) | 今作で初めてLisa GerrardとBrendan Perryはゲスト・ミュージシャンを迎えることなく、全ての楽曲の演奏を自分達のみで完成させている。基本的な音楽路線を変えることなく、トライバルな打楽器類や土の薫りのするサウンドスケープを形作るキーボード群は、Lisa GerrardとBrendan Perryの持つ音楽性を上手い具合にバランスを保つことに成功している。全体的にパーカッション類の比重が強くなった印象は受ける。オープニングのLisa Gerrardの深いコントラルトの響きを持つ"Yulunga"はオーストラリアの伝統的なサウンドを基にしているようだ。Brendan Perryの歌う"The Ubiquitous Mr Lovegrove"は後に映画「クロッシング・ガード」に使われる。"The Wind that Shakes the Barley"は18世紀のアイリッシュ・ソング(The Chieftans等がカヴァーをしている)。初期Clannadを思い出させる。どこまでも美しいサウンドを奏でるBrendan Perryの歌う"The Carnival is Over"は今作のハイライトの一つだろう。この曲と"Tell Me about the Forest"は歌詞や歌メロにJoy Divisionの影響もあるよう。"How Fortunate the Man with None"はBertolt Brechtの詞に曲を付けたもの。全体的に多彩なパーカッション類の使用と随所に配されたメロディアスな旋律が際立ったアルバムに仕上がっている。 |
 | Spiritchaser ('96) | オープニングから多彩なパーカッションが鳴り響く。Brendan PerryとLisa Gerrard以外にもパーカッション奏者に1stにも参加していたPeter Ulrich、アイリッシュ・フォーク・バンドKilaからLance Hogan、Ronan O'Snodaighが参加。そしてRobert Perryという人物がオープニング・ソングの"Nierika"と"Dedicace Outo"に参加。"Indus"ではターキッシュ・クラリネット奏者にRenaud Pionが参加。その"Indus"においてはストリングスやウドゥっぽい音が鳴るセクションではBeatlesの"Within You Without You"のメロディー・ラインが出てくる。メキシコ・ウイチョル族の言葉で「境界」を意味する"Nierika"、文字通りインド、インダスをモチーフにした"Indus"、ラテン・パーカッションから着想を得た"Song of the Dispossessed"、ジャングルにいるようなSEを効果的に配した神秘的な"Song of the Nile"とワールド・ビートの常連のような地名がアルバム全体を覆っており、今までの欧州的な所からの脱却が見られ、プリミティブなサウンドに回帰しようとする試みは新しい挑戦のようにも思えた。が、最後の"Devorzhum"でのLisa Gerrardの繊細なヴォーカルで、バンドとしても幕を閉じることになる。 |
 | Anastasis ('12) | 何と16年ぶりの復活作。タイトルも"Anastasis"とギリシャ語で「復活」を意味する、まさにズバリのタイトル。Lisa Gerrard、Brendan Perryともに映画音楽に携わり、本作ではオーケストレーションがグっと洗練されたものとなった。オープニングの"Children of the Sun"や"Opium"そして最後の"All in Good Time"などはBrendan Perryの深い声と優しいメロディーに長い不在期間などなかったかのような錯覚に陥る。オープニングのコンピューター音が森の中の鳥の囀りのようにも聴こえる不思議な融合を持つ"Anabasis"は古代ギリシャの作家/傭兵だったクセノポンの著作として有名。"Agape"は聖書で取り上げられる神の愛、普遍的な愛、という言葉。そこに中東的なバックグラウンドにフレーズに正にLisa Gerrardが舞う様が見て取れるような曲。古代において踊りは神へ献上するものだった、という。そんな事を連想させる。バグパイプから導かれる"Return of the She-King"のShe-Kingとは16世紀に女海賊として知られたGrace O'Malleyの事だろう。Dead Can Danceの楽曲の中で最もアイリッシュ色が濃い曲なのも頷ける。21世紀に生み出されたDead Can Danceの音はどこまでも慈愛に満ち、プリミティブなサウンドを緻密に紡ぎ上げた結果、洗練されたDead Can Dance独自の世界観へと昇華させた傑作の一つ。ジャケットはDead Can Danceのオフィシャル・サイトで販売されたデラックス盤仕様。 |
Other
 | This Mortal Coil "It'll End in Tears" ('98) | 4ADのレーベルオーナーIvo Watts-Russellが仕掛けたオールスタープロジェクト的なアルバム。Lisa Gerrard(vo)は"Waves Become Wings"、Cocteau TwinsのSimon Raymonde(g)とループ・アコーディオンのみで参加した浮遊感漂うインスト曲"Barramundi"、同じくDead Can DanceのBrendan Perryとの"Dreams Made Flesh"で参加。後者は正にDead Can Danceそのもの。"Barramundi"のみSimon Raymonde作で残りはLisa Gerrard作となっている。その他にもElizabeth Fraser(Cocteau Twins)歌うTim Buckleyの"Song to the Siren"やRoy Harperの"Another Day"がドリーミーなヴァージョンに仕上げている。またAlex Chilton(元Big Star)が作曲で冒頭の"Kangaroo"と"Holocaust"で参加。 |